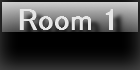● 「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」 ●
これまでの記事を初稿してから5年の歳月が過ぎた…。
西崎氏が“不在”の間、「宇宙戦艦ヤマト」というお宝コンテンツはどのように推移したのだろうか?
著作権保持者の(株)東北新社や、映像ソフト化権を持つ会社にとっては、会社の資産を有効に活用するのは当然であり、眠らせておくだけでは宝の持ち腐れでしかない。
だが西崎・松本裁判が法廷外和解になった後でも、「宇宙戦艦ヤマト」の新作を立ち上げようとする動きには横槍が浴びせられていたようである。
これは、有能なクリエーターや興行主が、「宇宙戦艦ヤマト」への新たに触手をのばすのを躊躇させる十分な力だった。
唯一数年間にわたり“横槍”に負けず新たな作品作りを模索し続けていた企業がある。(株)エナジオである。
エナジオの社長は、西崎義展氏の養子のうちの一人、「西崎彰司」氏だ。
同社は西崎・松本裁判和解後から、本格的に新作製作への足がかりを探して動いていた。
だが企画は消え、また立ち上げれば消える状態が実情で、「宇宙戦艦ヤマト」の新作を立ち上げる決定的な要素を、誰も持ち合わせていなかった。
2007年、状況は一変する。
西崎義展氏が贖罪を済ませ帰って来たのだ。
今まで誰もなしえなかった「宇宙戦艦ヤマト」の新作製作が、西崎氏の登場で一気に動き始めた。まさにカリスマの復活であった。
東北新社としても、このまま眠らせておくにはもったいないコンテンツに対して、具体的な動きが存在すれば使用の許諾を出さない手は無い。
また、「(株)セディックインターナショナル」が全面的に西崎氏の企画に参加したことは、新作実現への決め手へと繋がった。
とはいえ、疑問もある。10年から新作を作っていない、ヒット作は20年以上出ていない、しかも社会的に物議を醸す人物が現れたからと言って、話がトントンと進むのだろうか?これまでの10年間の歩みを見れば、著作権者がOKを出すことに強い疑念があった。
結果としては第三者の何か強い影響力があったのか、西崎氏周辺のスタッフが有能だったのか分からないが、新作映画化はスタートした。いずれにしても、今まで回らなかったことが西崎氏の登場で一気に動き出す。彼の凄みをまざまざと感じた。
製作現場での西崎氏は、70を越えても貪欲だった。
スタジオには劇場と同じクオリティー表現が出来るモニター一式を導入し、映像の1コマ1コマ、音楽の入りから終いまで、逐一担当者に指示を出していった。その姿は旧作時代の彼と変わらないエネルギッシュな姿であった。
ただそうした「西崎ヤマト」製作現場では、実質動いているクリエーターは苦労の連続であったようである。
リテイクの連続、昨日の変更点を今日見せれば、昨日へ戻せと…。
何の打ち合わせも無く「設定を変えたい」、「スタッフを変えたい」などなど、西崎氏の意向には相当苦労したようである。
だがスタッフの意気込みは、「宇宙戦艦ヤマト」というビッグネームを新たに生み出す誇りか気概か、衰えを知らなかった…。
もちろん西崎氏も最後まで妥協することなく、ほぼ完成したフィルムを練馬の森田編集室で深夜まで手直しする作業を続けた。
まさに「宇宙戦艦ヤマト」は、西崎義展の情熱を全て詰め込んだ作品なのだ。
そして2009年12月、ついに「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」が飛び立ったのだ。
西崎氏が“不在”の間、「宇宙戦艦ヤマト」というお宝コンテンツはどのように推移したのだろうか?
著作権保持者の(株)東北新社や、映像ソフト化権を持つ会社にとっては、会社の資産を有効に活用するのは当然であり、眠らせておくだけでは宝の持ち腐れでしかない。
だが西崎・松本裁判が法廷外和解になった後でも、「宇宙戦艦ヤマト」の新作を立ち上げようとする動きには横槍が浴びせられていたようである。
これは、有能なクリエーターや興行主が、「宇宙戦艦ヤマト」への新たに触手をのばすのを躊躇させる十分な力だった。
唯一数年間にわたり“横槍”に負けず新たな作品作りを模索し続けていた企業がある。(株)エナジオである。
エナジオの社長は、西崎義展氏の養子のうちの一人、「西崎彰司」氏だ。
同社は西崎・松本裁判和解後から、本格的に新作製作への足がかりを探して動いていた。
だが企画は消え、また立ち上げれば消える状態が実情で、「宇宙戦艦ヤマト」の新作を立ち上げる決定的な要素を、誰も持ち合わせていなかった。
2007年、状況は一変する。
西崎義展氏が贖罪を済ませ帰って来たのだ。
今まで誰もなしえなかった「宇宙戦艦ヤマト」の新作製作が、西崎氏の登場で一気に動き始めた。まさにカリスマの復活であった。
東北新社としても、このまま眠らせておくにはもったいないコンテンツに対して、具体的な動きが存在すれば使用の許諾を出さない手は無い。
また、「(株)セディックインターナショナル」が全面的に西崎氏の企画に参加したことは、新作実現への決め手へと繋がった。
とはいえ、疑問もある。10年から新作を作っていない、ヒット作は20年以上出ていない、しかも社会的に物議を醸す人物が現れたからと言って、話がトントンと進むのだろうか?これまでの10年間の歩みを見れば、著作権者がOKを出すことに強い疑念があった。
結果としては第三者の何か強い影響力があったのか、西崎氏周辺のスタッフが有能だったのか分からないが、新作映画化はスタートした。いずれにしても、今まで回らなかったことが西崎氏の登場で一気に動き出す。彼の凄みをまざまざと感じた。
製作現場での西崎氏は、70を越えても貪欲だった。
スタジオには劇場と同じクオリティー表現が出来るモニター一式を導入し、映像の1コマ1コマ、音楽の入りから終いまで、逐一担当者に指示を出していった。その姿は旧作時代の彼と変わらないエネルギッシュな姿であった。
ただそうした「西崎ヤマト」製作現場では、実質動いているクリエーターは苦労の連続であったようである。
リテイクの連続、昨日の変更点を今日見せれば、昨日へ戻せと…。
何の打ち合わせも無く「設定を変えたい」、「スタッフを変えたい」などなど、西崎氏の意向には相当苦労したようである。
だがスタッフの意気込みは、「宇宙戦艦ヤマト」というビッグネームを新たに生み出す誇りか気概か、衰えを知らなかった…。
もちろん西崎氏も最後まで妥協することなく、ほぼ完成したフィルムを練馬の森田編集室で深夜まで手直しする作業を続けた。
まさに「宇宙戦艦ヤマト」は、西崎義展の情熱を全て詰め込んだ作品なのだ。
そして2009年12月、ついに「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」が飛び立ったのだ。
website TOP