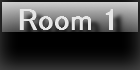● 「宇宙戦艦ヤマト」あってのファン ●
人は、驕りたかぶるものだ。
宇宙戦艦ヤマトのヒットは、イコール商業ベースでの大成功であった。
『西崎なら金を稼げる』子供向け戦略を仕掛ける企業はもちろん、他業種までこぞって西崎氏のもとを訪れた。
この状況を加速させた一番の要因が1978年に訪れる「さらば宇宙戦艦ヤマト〜愛の戦士たち〜」の製作・公開である。
この作品はアニメ史上まれにみる大ヒットとなり、後のアニメブームの火付け役となったばかりか、この作品を観て影響を受け、後の偉大なクリエーターになった人物は数多くいる。
世間が、「TVまんが」から「アニメ」になった記念碑的作品こそ、この映画だったのだ。
西崎氏はこの成功で一躍時の人となった。
もともと交友は広い人物ではあったが、西崎氏に集まる金の力はさらに人を呼び、黒い物も白だと言わしめる力があった。
またそんな西崎氏と同じように、ヤマトで注目を浴びた人物が他にもいた。
松本零士氏である。
松本零士氏も、ヤマトの成功で時の人となっていた。
当時の売れっ子作家となった松本氏のもとにも、漫画連載や、アニメ製作の話しが多く持ち込まれた。
当時の松本氏が携わらないアニメであっても、宇宙物が主流となり、キャラクターは1970年の風潮を引き継いだ髪形の「松本チック」なキャラばかりが登場したものだ。
アニメにおいて絵は命である。
宇宙戦艦ヤマトの成功が多くのクリエーターによる共同作業によるものとの真実は、一般視聴者には知る余地の無い事であり、当時の環境も「スタッフ」を大きく取り上げられる状況には無かった。これはイコール、松本零士氏の独壇場だったのだ。
宇宙戦艦ヤマトがマスコミで取り上げられるたびに、それに付き添うかのように松本氏も取り上げられ、彼を取り巻く人脈も広がったのだ。そして莫大な金と、名誉を彼にもたらした。
結果として宇宙戦艦ヤマトには、2人の産みの親が存在する事になった。
この2人の産みの親は、ヤマトの育て方に意見の相違を持っていた。これは西崎氏にとっては意見の相違であり、対立ではなかったのだが、松本氏にとっては「対立」に思えたのかもしれない。
さて西崎氏であるが、ヤマトの成功は結果として彼を変えてしまった。
世間が自分をチヤホヤする姿に、人間としての驕りが表面化したのであろう、当時の彼の写真や映像を見ると、明らかに顔が違うのだ。まるで怪しげな新興宗教の教祖様のようである。
映像の言葉尻をみても、強者が弱者に道を説くかのごとくな言い回しなのだ。
西崎氏は思っていただろう。「宇宙戦艦ヤマトの成功は、私のおかげだ。」と。これは、「宇宙戦艦ヤマトあってのファン」を意味し、「ファンあっての宇宙戦艦ヤマト」ではなかったのだ。
この頃の西崎氏は、1977年、劇場前に並んでいた多くの若者を見て涙したときの「彼」ではなかった。
しかし西崎氏の驕りたかぶりは、幸いにも長くはつづかなかった。
皮肉にも「ファンあっての宇宙戦艦ヤマト」を西崎氏に気づかさせたのは、自分が思うがままに企画したイベントに参加するファンの声や、大人とは違う純粋な感情しか持ち合わせない子供達の心を込めた手紙であったのだ。
輝く瞳で握手を求める子供達に、心が動かない者は少ない。
西崎氏は後に宇宙戦艦ヤマトファンクラブの集いでこう述べた。
「『ヤマト』のファンの集いというのがある限り、たとえそれが5人、10人になっても僕は必ず来ます。」西崎氏の、ファンに対する偽りのない言葉であろう。
また「ファンからはお金は取れない。」と無料で招待した、1984年のNHK交響楽団による「交響曲宇宙戦艦ヤマト」公演など、金儲けからは外れた行動を彼は幾つもとった。
全てが自分の思う様に動いていた時を経て、西崎義展という宇宙戦艦ヤマトを作った男は、ファンのありがたさ、怖さをしった。そして自分自身が何時しか、宇宙戦艦ヤマトのファンになっていたのだ。

website TOP
宇宙戦艦ヤマトのヒットは、イコール商業ベースでの大成功であった。
『西崎なら金を稼げる』子供向け戦略を仕掛ける企業はもちろん、他業種までこぞって西崎氏のもとを訪れた。
この状況を加速させた一番の要因が1978年に訪れる「さらば宇宙戦艦ヤマト〜愛の戦士たち〜」の製作・公開である。
この作品はアニメ史上まれにみる大ヒットとなり、後のアニメブームの火付け役となったばかりか、この作品を観て影響を受け、後の偉大なクリエーターになった人物は数多くいる。
世間が、「TVまんが」から「アニメ」になった記念碑的作品こそ、この映画だったのだ。
西崎氏はこの成功で一躍時の人となった。
もともと交友は広い人物ではあったが、西崎氏に集まる金の力はさらに人を呼び、黒い物も白だと言わしめる力があった。
またそんな西崎氏と同じように、ヤマトで注目を浴びた人物が他にもいた。
松本零士氏である。
松本零士氏も、ヤマトの成功で時の人となっていた。
当時の売れっ子作家となった松本氏のもとにも、漫画連載や、アニメ製作の話しが多く持ち込まれた。
当時の松本氏が携わらないアニメであっても、宇宙物が主流となり、キャラクターは1970年の風潮を引き継いだ髪形の「松本チック」なキャラばかりが登場したものだ。
アニメにおいて絵は命である。
宇宙戦艦ヤマトの成功が多くのクリエーターによる共同作業によるものとの真実は、一般視聴者には知る余地の無い事であり、当時の環境も「スタッフ」を大きく取り上げられる状況には無かった。これはイコール、松本零士氏の独壇場だったのだ。
宇宙戦艦ヤマトがマスコミで取り上げられるたびに、それに付き添うかのように松本氏も取り上げられ、彼を取り巻く人脈も広がったのだ。そして莫大な金と、名誉を彼にもたらした。
結果として宇宙戦艦ヤマトには、2人の産みの親が存在する事になった。
この2人の産みの親は、ヤマトの育て方に意見の相違を持っていた。これは西崎氏にとっては意見の相違であり、対立ではなかったのだが、松本氏にとっては「対立」に思えたのかもしれない。
さて西崎氏であるが、ヤマトの成功は結果として彼を変えてしまった。
世間が自分をチヤホヤする姿に、人間としての驕りが表面化したのであろう、当時の彼の写真や映像を見ると、明らかに顔が違うのだ。まるで怪しげな新興宗教の教祖様のようである。
映像の言葉尻をみても、強者が弱者に道を説くかのごとくな言い回しなのだ。
西崎氏は思っていただろう。「宇宙戦艦ヤマトの成功は、私のおかげだ。」と。これは、「宇宙戦艦ヤマトあってのファン」を意味し、「ファンあっての宇宙戦艦ヤマト」ではなかったのだ。
この頃の西崎氏は、1977年、劇場前に並んでいた多くの若者を見て涙したときの「彼」ではなかった。
しかし西崎氏の驕りたかぶりは、幸いにも長くはつづかなかった。
皮肉にも「ファンあっての宇宙戦艦ヤマト」を西崎氏に気づかさせたのは、自分が思うがままに企画したイベントに参加するファンの声や、大人とは違う純粋な感情しか持ち合わせない子供達の心を込めた手紙であったのだ。
輝く瞳で握手を求める子供達に、心が動かない者は少ない。
西崎氏は後に宇宙戦艦ヤマトファンクラブの集いでこう述べた。
「『ヤマト』のファンの集いというのがある限り、たとえそれが5人、10人になっても僕は必ず来ます。」西崎氏の、ファンに対する偽りのない言葉であろう。
また「ファンからはお金は取れない。」と無料で招待した、1984年のNHK交響楽団による「交響曲宇宙戦艦ヤマト」公演など、金儲けからは外れた行動を彼は幾つもとった。
全てが自分の思う様に動いていた時を経て、西崎義展という宇宙戦艦ヤマトを作った男は、ファンのありがたさ、怖さをしった。そして自分自身が何時しか、宇宙戦艦ヤマトのファンになっていたのだ。
website TOP